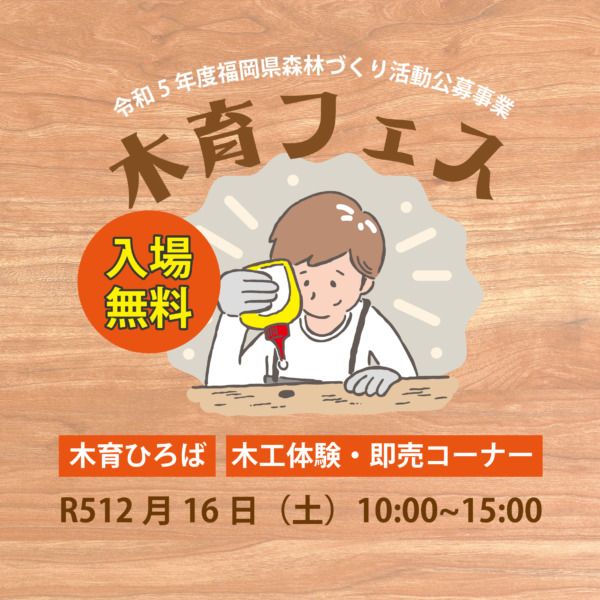気になっていた恵蘇八幡宮
朝倉を超えて吉井に向かう途中いつも通り過ぎる大きな神社
鳥居が大きくて階段の奥にある神社
ただもんじゃない感がしてて気になり今回はそこ目指して行ってみました。
ネットには
斉明天皇7年(661)建立。斉明天皇は百済救援のため朝倉町長安寺の橘広庭宮に皇居と大本営を遷されました。中大兄皇子(後の天智天皇)は国家安泰と武運長久を御祈願のため宇佐神宮の祭神 応神天皇の御霊を奉り朝倉山天降八幡と崇められました。その後 天武天皇の御代、白凰元年壬申(673)斉明・天智天皇の二神霊を勅命により合わせ祭り恵蘇八幡三柱大神と称しました。昔は上座郡中三十三村の総社でしたが現在は朝倉地域の総社氏神です。明治14年(1881)に郷社に列せられました。
御祭神
斉明天皇(第37代、第35代皇極天皇が重祚)
応神天皇(第15代)
天智天皇(第38代)
恵蘇八幡宮
〒838-1306
福岡県朝倉市山田166

入り口には猿田彦大神があります
猿田彦大神は「みちひらきの大神」として崇敬され、旅の安全の御神徳厚い神として祀られています。

綺麗なところだった

天智天皇と漏刻
「漏刻」これも初めてみたからネットの文章をもらいます。
天智天皇10年4月25日(ユリウス暦671年6月10日)天智天皇は水時計の漏刻を作り「時刻」を人々に知らせたと伝えられています。実物は分かっていませんが、中国で用いられた漏刻の形式を模倣したものと考えられています。
この漏刻は、4個の桶を段違いにならべたもので、第1番目を夜天地、第2を日天地、第3を平壺、第4を万水壺といい、万水壺の中には矢が立てられています。第1の壺に水を注ぐと、水は管を通って順番に一番下の壺である万水壺へと流れ込み、万水壺に水が溜まるにつれて、矢が浮き上がるようになり、矢に記された目盛りを読み取ることで時刻を知る仕組みとなっています。
現在、恵蘇八幡宮では6月10日(時の記念日)を記念して、毎年同日に式典が催されています。
ぁ、6月10日もうすぐじゃん!

御神木 クスノキ
軽内にあった大きな木 樹齢300年以上
立派だったわ〜

喪に服した中大兄皇子
中大兄皇子は、御陵山の山腹(現在の八幡宮境内)に木皮のついたままの丸木の柱を立て、板を敷き、芦の簾を掛け、苫をふき、あばらなる屋に、塊を枕にし、1日を1ヶ月に代えて12日間喪に服されたとされています。そのことから、この地は「木の丸殿」「黒木の御所」と呼ばれるようになりました。
と書いてる。
朝倉山(御陵山):斉明帝藁葬地

御朱印
神主さんは不在だったので御朱印はないかなと思ったら置いてた。
木箱に三百円入れたらもらえるやつ。
だもので日付はなしです。

もりもりした狛犬さん

ランチ
筑後吉井にあるいつも車がいっぱい止まってて入れなかったお店
そば処 郡上さん
お蕎麦食べたよ 今日は鴨つけ麺。
うち鴨つけ麺率高め
そば処 郡上
福岡県うきは市吉井町福益1628-1
営業時間
11:00~15:00
17:30〜20:00(オーダーストップ)
そば無くなり次第終了
定休日:木曜日